(2025年8月増補改訂)
加藤哲郎の研究の軌跡
■加藤「日本における『原子力の平和利用』の出発」,■『日本の社会主義ーー原爆反対・原発推進の論理』,■「SFとしての『原子力平和利用』」(その毎日新聞版、you tube版)。■「日独同盟に風穴をあけた日本人<崎村茂樹>探索」,■「情報戦のなかの『亡命』知識人」,■「社会民主主義の国際連帯と生命力」■「戦後米国の情報戦と60年安保ーーウィロビーから岸信介まで」,■「アメリカニズムと情報戦」,■「『国際歴史探偵』の20年」,■「731部隊二木秀雄の免責と復権」,![]() ■「戦争の記憶:ゾルゲ事件、731部隊、シベリア抑留」
■「戦争の記憶:ゾルゲ事件、731部隊、シベリア抑留」

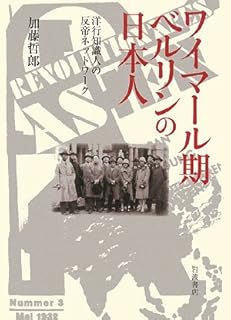
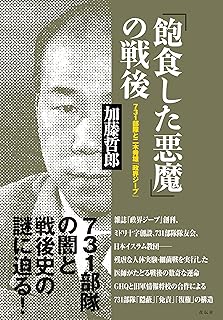
●2017.6.1 私の久しぶりの書きおろし『「飽食した悪魔」の戦後ーー731部隊・二木秀雄と「政界ジープ」』は、5月25日に花伝社から刊行されました。満州侵略の関東軍731細菌戦部隊の、敗戦後における隠蔽・免責・復権のメカニズムと、731部隊医師・二木秀雄『政界ジープ』対佐和慶太郎『真相』の、戦後10年にわたる時局雑誌の興亡が目玉です。400頁税込み3780円とやや高価ですが、アマゾンやお近くの書店で、ぜひお求めください。●2018.5.1 『「飽食した悪魔」の戦後』の姉妹編、改訂普及版でもある『731部隊と戦後世界ーー隠蔽と覚醒の情報戦』が花伝社から刊行されました。●2025.2 2 必要に迫られて、デジタル化が遅れていた1960−90年代の論文を、できるだけ原文のPDFになるようにコピーし、収蔵しました。著書に収録した論文もありますが、『現代と思想』を受け継いだ西山俊一さん編集の『季刊 窓』の諸論文など、特に1989−91年の東欧革命・冷戦崩壊・ソ連解体期の生々しい記録を、ご賞味ください。論文によっては縦横逆の場合もありますから、PDFをダウンロードした上でお読みになった方がいい場合があります。ただし著書に匹敵する大部の論文は、サイト容量との関係で問題があり、入っていません。
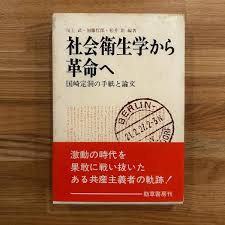


- 『社会衛生学から革命へ——国崎定洞の手紙と論文』(川上武・松井坦と共編 著、勁草書房、1977年)
- 『シンポジウム 核時代と世界平和』(岩崎允胤・熊倉啓安・土生長穂・服部学と共著(大月書店、1981年)A.
- 『国家論のルネサンス』(青木書店、1986年) (書評 海野八尋、清家正義、五十嵐仁) 、
 『これからの日本を読む』(伊藤正直らと共著、労働旬報社、1987年)
『これからの日本を読む』(伊藤正直らと共著、労働旬報社、1987年) 『ジャパメリカの時代に――現代日本の社会と国家』(花伝社、1988年、The Age of JAPAMERICA”,英文国際会議報告1988)
『ジャパメリカの時代に――現代日本の社会と国家』(花伝社、1988年、The Age of JAPAMERICA”,英文国際会議報告1988) 『戦後意識の変貌』(岩波ブックレット「戦後史」第14冊、1989年) (書評 中国新聞)
『戦後意識の変貌』(岩波ブックレット「戦後史」第14冊、1989年) (書評 中国新聞)- 『社会主義と組織原理 1』(窓社、1989年) (書評 田口富久治)
 『東欧革命と社会主義』(花伝社、1990年) (書評 中国新聞、長崎浩、南塚信吾)(
『東欧革命と社会主義』(花伝社、1990年) (書評 中国新聞、長崎浩、南塚信吾)(- 『社会主義の危機 と民主主義の再生――現代日本で市民であること』(教育史料出版会、1990年) <
 『東京――世界都市化の構図』(吉原直樹らと共著、青木書店、1990年)
『東京――世界都市化の構図』(吉原直樹らと共著、青木書店、1990年)
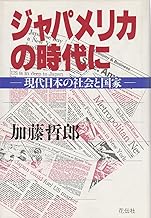
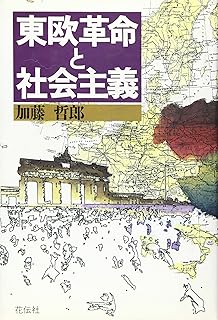

- 『東欧革命と社会主義(韓国語版)』(Hanultang Press,1990)
- 『コミンテルン の世界像――世界政党の政治学的研究』(青木書店、1991年) (書評 佐々木力、栗木安延、富田武、、山根献、石川捷治、百瀬宏、岩村登志夫、神田文人、安田浩、毎日新聞、村岡到)
- Is Japanese Capitalism Post-Fordist?“(with Rob Steven, Japanese Studies Centre, Melbourne, 1991
- 『短い二〇世紀の総括――回転した世界史を読む』(田口富久治らと共著、教育 史料出版会、1992年)
- 『ソ連崩壊と社会主義――新しい世紀へ』(花伝社、1992年)
 『社会と国 家』(岩波書店、1992年)
『社会と国 家』(岩波書店、1992年)- 『社会主義像 の展相』(大薮龍介らと共編著、世界書院、1993年)
 『国際論争 日本型経営はポスト・フォーディズムか?』(英和両版、ロブ・ス ティーヴンと共編著、窓社、1993年)
『国際論争 日本型経営はポスト・フォーディズムか?』(英和両版、ロブ・ス ティーヴンと共編著、窓社、1993年) 『現代市民社会 と企業国家』(平田清明らと共著、御茶の水書房、1994年)
『現代市民社会 と企業国家』(平田清明らと共著、御茶の水書房、1994年) 『企業社会と偏差値』(中内敏夫らと共著、藤原書店、1994年)
『企業社会と偏差値』(中内敏夫らと共著、藤原書店、1994年) 『ローザ・ルクセンブルクと現代世界』(伊藤成彦らと共著、社会評論社、19 94年)
『ローザ・ルクセンブルクと現代世界』(伊藤成彦らと共著、社会評論社、19 94年)
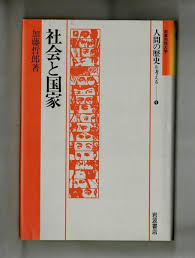


- 『モスクワで粛清 された日本人――30年代共産党と国崎定洞・山本懸蔵の悲劇』(青木書店、199 4年) (書評 桜井智志, 川西英通)
- 『国民国家のエル ゴロジー――「共産党宣言」から「ッ衆の地球宣言」へ』(平凡社、1994年)
- 『人間 国崎定 洞』(川上武と共著、勁草書房、1995年)
- 『現代日本のリズ ムとストレス――エルゴロジーの政治学序説』(花伝社、1996年)
- 『揺れ動く現代 への視座』(佐藤和夫・伊藤正直と共著、三省堂、1997年)
- 『日本史のエッセン ス』(荒木敏夫・保坂智らと共著、有斐閣、1997年)
- 『近代日本社会運動史人物大事典』(編集委員、全5巻、日外アソシエーツ、 1997年、約30項目執筆)
 『日本史 辞典』(永原慶二らと共編、岩波書店、1999年)
『日本史 辞典』(永原慶二らと共編、岩波書店、1999年)
『グラムシは世界 でどう読まれているか』(共編、社会評論社、2000年) 『20世紀を超えて─ ─再審される社会主義』(花伝社、2001年)
『20世紀を超えて─ ─再審される社会主義』(花伝社、2001年)- 『20世紀の夢と現 実:戦争・文明・福祉』(渡辺雅男と共編、彩流社、2002年)
- 『島崎蓊助自伝──父・藤村への 抵抗と回帰』(島崎爽助と共編、平凡社、2002年)
- 『国境を越えるユートピ ア──国民国家のエルゴロジー』(平凡社ライブラリー、2002年)
- 『国立市議会史』記述編(田崎宣義と分担執筆、国立市議会、 2003年、非公式インタ ーネット版)
 Japanese Political Economy in Restructuring: Lessons for Indian Development(in , Sushila Narsimhan & G.Balatchandirane eds., INDIA AND EAST ASIA: LEARNING FROM EACH OTHER, Manak, Delhi 2004)
Japanese Political Economy in Restructuring: Lessons for Indian Development(in , Sushila Narsimhan & G.Balatchandirane eds., INDIA AND EAST ASIA: LEARNING FROM EACH OTHER, Manak, Delhi 2004)- 加藤・鳥山・森・国場編『戦後初期沖縄解放運動資料集』全3巻(共編、不二出版 、2004-2005年)
- 『象徴天皇制の起源 アメ リカの心理戦「日本計画」』(平凡 社新書、2005年) (書評 八代拓)
 加 藤哲郎・伊藤晃・井上學編著『社会運動の昭和史――語られざる深層』(白順社 、2006)
加 藤哲郎・伊藤晃・井上學編著『社会運動の昭和史――語られざる深層』(白順社 、2006)- 『情報戦の時代ーーインターネットと劇場政治』(花伝社 、2007)
- 『情報戦と現代史ーー日本国憲法へのもうひとつの道』(花伝社 ,2007)
 加藤哲郎・国廣敏文編『グローバル化時代の政治学』(法律文化社、2008年3月)
加藤哲郎・国廣敏文編『グローバル化時代の政治学』(法律文化社、2008年3月)- 『ワイマール期ベルリンの日本人ーー洋行知識人の反帝ネットワーク』(岩波書店、2008年10月)



- 加藤哲郎、小野一、田中ひかる、堀江孝司編著『国民国家の境界』(日本経済評論社、2010年5月)
- 加藤哲郎・今井晋哉・神山伸弘編『差異のデモクラシー』(日本経済評論社、2010年6月)
- 合澤清・加藤哲郎・日山紀彦編『危機の時代を観る』(社会評論社、2010年6月)
- 加藤哲郎・丹野清人編『21世紀への挑戦 7 民主主義・平和・地球政治』(日本経済評論社、2010年11月)
- 加藤哲郎『汕頭市(貴嶼村)の現状からみる 中国の経済発展と循環型社会構築への課題』(信州大学イノベーション研究・支援センター、2011年3月 )
- 矢吹晋・加藤哲郎・及川淳子『劉暁波と中国民主化の行方』{花伝社、2 011年4月)
 加藤哲郎・井川充雄編『原子力と冷戦ーー日本とアジアの原発導入』(花伝社、2013年3月)
加藤哲郎・井川充雄編『原子力と冷戦ーー日本とアジアの原発導入』(花伝社、2013年3月) 加藤哲郎『日本の社会主義ーー原爆反対・原発推進の論理』(岩波現代全書、2013年12月)
加藤哲郎『日本の社会主義ーー原爆反対・原発推進の論理』(岩波現代全書、2013年12月)- 『ゾルゲ事件ーー覆された神話』(平凡社新書、2014年3月)正誤表
- 加藤哲郎編集・解説『CIA日本人ファイル』全12巻(現代史料出版、2014年7月)、「解説」(第1巻所収)
 Michiko Tanaka, KATO Tetsuro et.al.eds.(田中道子・加藤哲郎他編), Política y pensamiento político en Japón 1926-2012 (スペイン語『近現代日本政治資料集 1926-2012年』),Departmento de Publicaciones, México, El Colegio de México(メキシコ大学院大学出版会, 2014)
Michiko Tanaka, KATO Tetsuro et.al.eds.(田中道子・加藤哲郎他編), Política y pensamiento político en Japón 1926-2012 (スペイン語『近現代日本政治資料集 1926-2012年』),Departmento de Publicaciones, México, El Colegio de México(メキシコ大学院大学出版会, 2014)- 加藤哲郎監修・解説『近代日本博覧会資料集成 紀元2600年記念日本万国博覧会』(国書刊行会、2016)、監修者解説「幻の紀元2600年万国博覧会ーー東京オリンピック、国際ペン大会と共に消えた『東西文化の融合』」(別冊)
 加藤哲郎編集・解説『CIA日本問題ファイル』全2巻(現代史料出版、2016年3月)「解説」(第1巻所収)
加藤哲郎編集・解説『CIA日本問題ファイル』全2巻(現代史料出版、2016年3月)「解説」(第1巻所収)- 『「飽食した悪魔」の戦後ーー731部隊・二木秀雄と「政界ジープ」』(花伝社、2017年5月)
- 『731部隊と戦後世界ーー隠蔽と覚醒の情報戦』(花伝社、2018年4月)
- 『ゾルゲ事件史料集成――太田耐造関係文書』 全10巻(不二出版、2019年7月ー2020年8月、毎日新聞報道、朝日新聞報道)加藤哲郎「解説ーーゾルゲ事件研究と『太田耐造文書』」
 『パンデミックの政治学ーー「日本モデル」の失敗』(花伝社、2020年10月)
『パンデミックの政治学ーー「日本モデル」の失敗』(花伝社、2020年10月) 加藤哲郎・小河孝『731部隊と100部隊ーー知られざる人獣共通感染症研究部隊』(花伝社、2022年8月,)
加藤哲郎・小河孝『731部隊と100部隊ーー知られざる人獣共通感染症研究部隊』(花伝社、2022年8月,) 獣医学者・小河孝さん、歴史学者・松野誠也さんとの共著『検証・100部隊ーー関東軍軍馬防疫廠の細菌戦研究』(花伝社、2024年9月)
獣医学者・小河孝さん、歴史学者・松野誠也さんとの共著『検証・100部隊ーー関東軍軍馬防疫廠の細菌戦研究』(花伝社、2024年9月)

主要論文――エッセイ、座談会など



- <1965−1978 大月書店編集部、マルクス・エンゲルス・レーニンの批判的検討>
- 加藤哲郎・金沢真・河内謙策・松井坦「野呂榮太郎論」『文化評論』1972年9月
- 加藤哲郎・河内謙策「野呂栄太郎の二つの戦線での闘争」『経済』1974年5月
- 「国崎定洞論――日本労働運動史と国際労働運動史の統一的把握のために」労働運動史研究会『日本の統一戦線運動』労働旬報社、1976年
- 「ゴータ綱領批判」」『マルクス主義法学講座』第8巻、日本評論社、1977年
 「初期コミンテルンにおける国家と革命」「コミンテルン第7回大会の国家像」『マルクス主義法学講座』第2巻>、日本評論社、1978年
「初期コミンテルンにおける国家と革命」「コミンテルン第7回大会の国家像」『マルクス主義法学講座』第2巻>、日本評論社、1978年- <名古屋大学法学部・一橋大学専任講師、ネオ・マルクス主義・ユーロコミュニズム研究>
- 「ユーロコミュニズムの射程」『マルクス主義研究年報』1978年
- 「世界政党と政策転換」名大『法政論集』78-79号、1979年
- 「国家の相対的自立性と構造的制約性」『法の科学』7号、1979年
- 「コミンテルンの綱領問題」名大『法政論集』80-83号、1979-80年
- 「先進国革命試論」『講座 現代資本主義国家』第4巻、大月書店、1980年
- 「コミンテルンの日本像(1929-31年)『一橋論叢』84巻5号、980年
 「政治イメージの政治学」『一橋論叢』85巻4号、1981年4月
「政治イメージの政治学」『一橋論叢』85巻4号、1981年4月- 「現代世界認識の構図—全般的危機論の批判的検討」『唯物論研究』4号、1981年5月
- 「現代社会における平和の理念と課題」『季刊 教育運動研究』16号、1981年12月
- 「教官から新入生へのことば」『全院協ニュース』1982年5月11日
- 「西欧マルクス主義の国家論と政治学」日本政治学会『現代国家の位相と理論』岩波書店、1982年
- 「32年テーゼの周辺と射程――コミンテルンの中進国革命論」『思想』693・694号、1982年3・4月
- 「地域政治形成論序説ーー新潟県三条市」一橋大学社会学部『地域社会の発展に関する比較研究』1983年3月
- 「棄権層・無党派層と戦後民主主義」二宮厚美・古城利明との座談会、『住民と自治』1983年6月
 「ネオコーポラティズム討論について」『一橋論叢』89巻1号、1983年
「ネオコーポラティズム討論について」『一橋論叢』89巻1号、1983年- 「現代日本国家論の方法–Rob Stevenの階級分析に寄せて」『一橋論叢』92巻6号、1984年
- 「経済大国日本と戦後国民意識」『歴史学研究』1984年1月
- 「自治・共同の原理を探る学際的討論」『住民と自治』1984年1月
- 「活字離れと青年の保守化」『ほんとぽあ』41、1984.5
- A Preliminary Note on the State in Contemporary Japan, Hitotsubashi Journal of Social Studies,Vol.16, No.1, 1984.
- 「権威主義的ポピュリズムをめぐって」『思想と現代』2号、1985年
- 「ロッキード問題の構造」『法と民主主義』196号、1985年4月
- 「戦後日本社会の変容と変革の展望」渡辺治・高橋祐吉・安田浩との座談会、『労働法律旬報』1111-12,1985年1月
- 「一つの国家論入門」『日本の科学者』1985年5月
- Marxist Debates on the State in Post-war Japan(with Fukuji Taguchi),Hosei Ronshu(A Journal of Law and Political Science),No.105(August 1985),Nagoya University.
- 「現代国家と地域生活者」『地域と自治体』15集、自治体研究社、1986年
- 「近代日本の歴史はどう描かれるべきかーー臨教審の歴史観・社会観」『労働法律旬報』1138号、1986.2.26
 「都市の政治意識の今日的諸相」一橋大学社会学部『多摩圏の総合的研究』1986年3月
「都市の政治意識の今日的諸相」一橋大学社会学部『多摩圏の総合的研究』1986年3月- 「国際化の中の日本労働者階級」『私の選択。あなたの選択』(労働旬報社、1986)
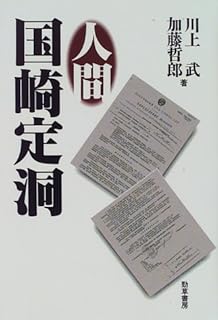


<訪米後一橋大学助教授・教授、東欧革命・ソ連崩壊>
- 「ユーロコーポラティズム論争」『木鐸』36号、1986年4月
- 「戦後史への複眼的視覚ーー世界システムから見た日本社会の変貌」1986年度大会報告『歴史学研究』1986
- 「戦前日本のマルクス主義国家論」『一橋論叢』97巻2号、1987年2月
- 「現代資本主義の国家形態」藤田勇編『権威的秩序と国家』東京大学出版 会、1987年、所収
- Der Neoetatismus im heutigen Japan, Prokla, Nr.77, 1987.
- 「日本が社会主義と映る時代」『葦牙』10号、1988年冬
- 「さまざまなアメリカ」『一橋大学ニュース』1988年7−8月
- 「構造的暴力としての日本型産業平和」『教育』498号、1988年8月
- 「天皇賛美の政治的狙い」一橋大学教職員組合『いま、天皇制はつくられる』1989年2月
- 「世界システムのなかの象徴天皇制」『思想と現代』19号、1989年
- 「日本人は金持ちか」(『日本近代史の虚像と実像』4,大月書店、1989年)
- 「現代日本資本主義と象徴天皇制」『季刊窓』創刊号、1989年秋>
 「国家権力の社会による再吸収と社会主義」『一橋論叢』102巻2号、1989年
「国家権力の社会による再吸収と社会主義」『一橋論叢』102巻2号、1989年-
 「「ポスト・フォード主義か、ウルトラ・フォード主義か」『季刊 窓』2号、 1989
「「ポスト・フォード主義か、ウルトラ・フォード主義か」『季刊 窓』2号、 1989 - The Age of “Japamerica”—Taking Japanese Development Seriously, Hitotsubashi Journal of Social Studies,Vol.21, No.1, 1989.
- 「社会主義の今後の行方」生協インタビュー『ほんとぴあ』1989年11月15日
 「東欧革命から世界の民衆は何を学ぶか」神奈川大学人文学会『人文研究』108号、1990年12月
「東欧革命から世界の民衆は何を学ぶか」神奈川大学人文学会『人文研究』108号、1990年12月 「国民国家から世界国家へ?」田中浩編『現代世界と国民国家の将来』御茶の 水書房、1990年、所収
「国民国家から世界国家へ?」田中浩編『現代世界と国民国家の将来』御茶の 水書房、1990年、所収- 「多国籍企業と国民国家・序説」『一橋論叢』105巻2号、1990年
- 「科学的真理の審 問官ではなく、社会的弱者の護民官に」松岡英夫・有田芳生編『日本共産党への手 紙』教育史料出版会、1990年、所収
 「日本資本主義はポスト・フォード主義か?」R・スティーヴンと共著、『季 刊 窓』4号、1990年
「日本資本主義はポスト・フォード主義か?」R・スティーヴンと共著、『季 刊 窓』4号、1990年- 「日本はポスト・フォード主義か」『労働運動研究』251号、1990年9月
- 「東欧市民革命と世界一の君主国ニッポン」『立命評論』92号、1990 年
 「社会主義の危機の哲学的諸相」『思想と現代』23号、1990年
「社会主義の危機の哲学的諸相」『思想と現代』23号、1990年 「現代の市民社会イメージと世界の中の日本」『葦牙』12号、1990年3月
「現代の市民社会イメージと世界の中の日本」『葦牙』12号、1990年3月- 「現代日本社会の構造と民主主義」『教育』520号、1990年4月
 「東欧市民革命から何を学ぶか」『龍谷法学』23巻2号、1990年9月
「東欧市民革命から何を学ぶか」『龍谷法学』23巻2号、1990年9月 藤井一行・平田清明・橋本剛との座談会「民主集中制ーー放棄か、堅持か、改革か」上下『季刊 窓』4−5号、1990
藤井一行・平田清明・橋本剛との座談会「民主集中制ーー放棄か、堅持か、改革か」上下『季刊 窓』4−5号、1990- 対談 加藤哲郎・今村仁司・横張誠「資本主義の未来」『現代思想』19巻8号、1991年
- 対談 加藤哲郎・小谷汪之・津田雅夫「<国家・民族・個人>再考」『思想と現代』25号、1991年4月
- 「東欧革命の日本的受容」『季刊窓』8号、1991年夏
 「歴史の真実と真理への接近」『葦牙』14号、1991年12月
「歴史の真実と真理への接近」『葦牙』14号、1991年12月 「コミンテルンとは何であったか」『フォーラム90s』5号、1991年2月
「コミンテルンとは何であったか」『フォーラム90s』5号、1991年2月 「分化するジャパノロジー」『季刊窓』10号、1991年冬
「分化するジャパノロジー」『季刊窓』10号、1991年冬- 「日本の社会構造の変化」『現代と展望』32号、1991年冬
- 「『反ファシズム統一戦線』研究の新段階」『一橋論叢』106巻4号、19 91年
- 「日ソ関係についての雑感」ソビエト研究所『ビュレティン』15号、1991年6月
- 「社会科学のボーダーレス化を実感」国際コミュニケーション基金『ICF』5号、1991年10月
- 「パクスアメリカーナの動揺は日本をどう変えるか」A>『歴史地理教育』470 号、1991年3月
- 「グラムシからネオ・マルクス主義へ」『朝日百科 世界の歴史』122号、 朝日新聞社、1991年
- Japanese Perception of the 1989 Eastern European Revolution,Hitotsubashi Journalof Social Studies, Vol.23, No.1, 1991.
- 「平和と怠ける権利を庶民の哲学に」『ニッポンをどうする』労働旬報社、1991年
- 「究極の政党の実験のあとでーー短い20世紀とソ連共産党解散の意味」『世界』1992年2月
- <一橋大学から旧ソ連秘密文書・日本人粛清犠牲者発掘>
- A・ゴードン、後藤道夫との対談「日本の企業と労働を問う」『労働法律旬報』1985号、1992年4月
- 「多国籍企業と国民国家・序説」『一橋論叢』105巻2号、1992年
- 「知識人としてのグラムシの実像ーー片桐薫書評」『季刊 窓』11号、1992
- 「日本の国家形成と国民形成」科研報告書『戦間期日本資本主義の国家像』1992年
- 「現存社会主義の崩壊をどう教えるか」『三省堂高校通信』1992年1月1日
- 「生き続ける理念・思想」(朝日新聞インタビュー1992年1月18日)
- 朝日新聞企画報道室『どうみる社会主義の行方』新興出版社、1992年「スウェーデンモデルか、日本モデルか」『経済評論』1992年8月号
- 「今問い直す日本の社会主義」『東大新聞』1992年9月1日
- 「現代における社会民主主義の諸相」和田春樹・小森田秋夫・近藤邦康編『社 会主義――それぞれの苦悩と模索』日本評論社、1992年、所収
- 「ソ連邦74年の政治的意味」『ソビエト研究』第8号、1992年
- 「21世紀の行方」『大東法学』19号、1992年1月
- Organisationstheorie Rosa Luxemburgs—Geburt und Scheitern der KPD-Satzung von 1919 als “Dezentralisierte Assoziation”, Hitotsubashi Journal of Social Studies,No.24, No.1, 1992.
- 一橋大学加藤ゼミ特集、『週刊読売』1992.12.27
- 「等身大のマルクスといかにつきあうか」今村仁司・山田鋭夫との対談『エコノミスト』1993年1月5日
- 「グラムシからポスト・マルクス主義へ」片桐薫・黒沢惟昭編『グラムシと現 代世界』社会評論社、1993年
- 「ラルフ・ミリバンド」白鳥令編『現代政治学の理論』中、早稲田大学出版局、1993
- 「占領世代2世は選挙を面白くできるか」『読書のいずみ』55号、1993年夏
- 「現代マルクス主義とリベラリズム」『レヴァイアサン』13号、1993年秋
- 「企業社会の克服に向かって」二宮厚美・伊藤正直・高橋祐吉との座談会『労働法律旬報』1993年1月
- 「現代資本主義を読み解く」『公明』1993年11月」
- 「日本人は勤勉で働き過ぎなのか」小池和男、宮田登と座談会『Communication』No,46,1993.12
- 「脱労働の社会主義へ」『月刊フォーラム』1993年9月
- 「ほめ殺しと脱労働の社会主義」大藪龍介・加藤哲郎ほか『社会主義像の展相』世界書院1993年
- 「過労死とサービス残業の政治経済学」日韓市民フォーラム報告『月刊フォーラム』1993年6月
- 「クルマ社会へ突進する中国」『月刊フォーラム』1993年7月
- Japanese Perceptions of the 1989 Eastern European Revolution, in Ian Neary ed.,War, Revolution and Japan, Japan Library, Sandgate 1993.
- 「自然死でもいいではないか」『左翼の滅び方について』窓社。1993年
- 大沢真理・川人博と座談会「過労死・家事労働・資本主義」『季刊 窓』17号、1993年
- 「歴史における善意 と粛清」『季刊 窓』第19号、1994年
- 対談:加藤哲郎・小林峻一「密告と粛清」『諸君』1994年8月
- 「現存社会主義の崩壊とその後」京都大学哲学・科学研究会『逍遥』第2号、1994年4月
 「過労死と過労兒のエルゴロジー」中内敏夫/加藤哲郎ほか『企業社会と偏差値』藤原書店、1994
「過労死と過労兒のエルゴロジー」中内敏夫/加藤哲郎ほか『企業社会と偏差値』藤原書店、1994- 「過労死とサービス残業の政治経済学」平田清明ほか『現代史民社会と企業国家』お茶の水書房、1994年
- 「ローザ・ルクセンブルグが構想した党組織」『ローザ・ルクセンブルグと現代世界』社会評論社。1994年
- 「日本人の勤勉神話ができるまで」『エコノミスト』1994年9月13日
- 和田春樹との対談「問題としての野坂参三」『季刊 窓』22終刊号、1994
- The Political Economy of Japanese KAROSHI(Death from Overwork), Hitotsubashi Journal of Social Studies, Vol.26, No.2, December 199
- 「戦後日本の国際的枠組みの確立と崩壊ーー冷戦体制と日米安保のエルゴロジー」坂野潤治ほか編『戦後改革と現代社会の形成』岩波書店、1994年
- 「したたかな戦後」『月刊フォーラム』1995年1月
- Workaholism— It’s not in the Blood, Look Japan, February 1995
 「現代日本的労働時間与政府的作用――過労死的政治経済学」中国語、復旦大 学日本研究中心『日本政府在経済現代化道程中的作用』復旦大学出版社、上海、19 95年
「現代日本的労働時間与政府的作用――過労死的政治経済学」中国語、復旦大 学日本研究中心『日本政府在経済現代化道程中的作用』復旦大学出版社、上海、19 95年- 「国境を越える夢 と逆夢」『月刊百科』393号、1995年7月)
- 「『世間』と『社 会』の相克」『「近現代史」の授業改革』創刊号<『社会科教育』別冊第412号 >、明治図書、1995年9月
- Is Japanese Capitalism Post-Fordist?”(with Rob Steven,in J.P.Arnason and Yoshio Sugimoto eds, Japanese Encounters With Postmodernity, Kegen Paul International, London/New York 1995.
- 「パーティは終わった、次は何を」『月刊フォーラム』1995年9月
- 「戦後高度成長を問う」国連・憲法問題研究会『「戦後日本」解体マニュアル』1995年10月
- 「現代資本主義分析とレギュラシオン理論」 Marxism & Radicalism Review,No.5,1995.12.4
- 「粛清連鎖のなかの 国崎定洞」(『思想の科学』1996年3月号)
- フォーラム90s討論「ユートピアと現実性」『月刊フォーラム』1996年3月
- シンポジウム「清水愼三『戦後革新の半日陰』をめぐって」『労働経済旬報』1996年4月
- 対談:加藤哲郎・中野徹三「いま20世紀の社会主義を検証する」『月刊フォーラム』1996年5月
- 代々木ゼミインタビュー「社会学部とは」(YOZEMI JOURNAL, 1996.6)
- 「政治と情報―― 旧ソ連秘密文書の場合」(『社会と情報』創刊号、東信堂、1996年7月)
- 「エルゴロジーとは臨界体力学とみつけたり」『人類働態学会会報』73号、1996,5.1)
- 「ワイマール期在 独日本人のベルリン社会科学研究会」(『大原社会問題研究所雑誌』455号、19 96年10月)
- 「国家論」 (『AERAMOOK 政治学がわかる』朝日新聞社、1996年、所収)
- 「金脈批判以上 の衝撃――『日本共産党の研究』」(『文藝春秋11月臨時増刊号・立花隆のすべ て』 、1996年、単行本『立花隆のすべて』文藝春秋社、1998年、同文春文庫 版、2001再録)
- L’economie politique de karoshi japonais, Perspectives Asiatiques, Automne 1996, Paris.
- 「現代とエルゴロジー」『揺れ動く現代への視座』三省堂、1997
- 「ベルリン反帝グ ループと新明正道日記」(新明正道『ドイツ留学日記』時潮社、1997年、所収)
- 「永続民主主義 革命の理論・その後――マルクス主義・市民社会・民主主義」(『月刊フォーラム』 1997年8月号)
- 「市民社会の政治学」河合塾『学問の鉄人』宝島社、1997
 Die politische Okonomie des japanischen Karoshi: Der Tod durch Uberarbeitung und das Konzept einer >>Ergologie<<, “Das Argument “, Nr. 218/1997(どうもこれがデンマーク語に訳されたらしい”Karosh i: Dソd af overarbejde- et voksende problem i Japan“)
Die politische Okonomie des japanischen Karoshi: Der Tod durch Uberarbeitung und das Konzept einer >>Ergologie<<, “Das Argument “, Nr. 218/1997(どうもこれがデンマーク語に訳されたらしい”Karosh i: Dソd af overarbejde- et voksende problem i Japan“)- The Japanese Victims of Stalinist Terror in the USSR(ドイツ・マンハイム大学の『歴史的共産主義研究年鑑』1998年版収録独文論 文の英語オリジナル)
- 「市民とア カデミズムと知識人」(H・田中との往復書簡、『葦牙』24号、1998年3月)
- 「コミンテルンとは何であったか」(『月刊フォーラム』1998年5月)
- 「『共産党 宣言』の現代的意味」(『経済と社会』第12号、1998年冬季号)
- 「『32年テ ーゼ』と山本正美の周辺」(『山本正美裁判資料論文集』新泉社、1998年、解 説)「20世紀社会 主義とは何であったか」 (社会主義理論学会編『20世紀社会主義の意味を問う』御 茶の水書房、1998年、所収)
- 「モスクワ でみつかった河上肇の手紙」(『大原社会問題研究所雑誌』1998年11月号)
- 「戦後日本と 『アメリカ』の影」(『歴史学研究』1998年大会特集号)
- 「1922 年9月の日本共産党綱領(上・下)」(『大原社会問題研究所雑誌』1998年12 月号・99年1月号)
- 「短い20世紀の脱神話 化」(思想の言葉,『思想』1999/1)
- Biographische Anmerkungen zu den japanischen Opfern des stalinistischen Terrors in der UdSSR, in, Hermann Weber hrsg., Jahrbuch fuer Historische Kommunismusforschung 1998, Akademie Verlag, 1998 Berlin.
- 「フォーラム型運動の21世紀へ」(『月刊フォーラム』週刊号、1999年3月)
- 「第一次共産党 のモスクワ報告書(上・下)」(『大原社会問題研究所雑誌』1999年8月・11 月、『日本史学年次別論文集 近現代3 1999年』学術文献刊行会、2002年)
- 「インターネットで社会科学」(アソシエ21ニューズレター、1999年7月)
- 「インターネ ットで歴史探偵」(web特別版、『歴史評論』1999年10月 )
- 「マルクス は共産主義社会を究極の目標としたか」(『アエラムック マルクスがわかる』朝日 新聞社、1999年、所収)
- From a Class Party to a National Party : Japanese communist party survives through the worldwide decline of communist parties ( AMPO, Vol.29, No.2, March 2000, )
- 「自治体労働者と地域住民との連携が暮らしやすい地方自治を 創り出す」(吉田紀世子、中島剛二との座談会、『月刊 東京』201号、2000年3月 15日号)
- 「社会主義」(山之内靖 との対談、『世界別冊 この本を読もう』2000年4月)
- 「『非常時共産党』の真 実──1931年のコミンテルン宛報告書」(『大原社会問題研究所雑誌』2000年 5月)(PDF版 )
- 「ロングビーチ事件」 (『沖縄を知る事典』日外アソシエーツ、2000年5月)
- 「高度経済成長は何を変えたか」 (『別冊歴史読本 日本史研究最前線』、2000年5月)
- 「『神の国・国体護 持』の政治家を21世紀『日本の顔』にするのか」(『週刊金曜日』2000年6月23日 号)
- 「ドイツ・スイスでの竹 久夢二探訪記」(『平出修研究』第32集、2000年6月)「グラムシと世界 国際シンポジウム序言」A>
- 『グラムシは世界でどう読まれているか』(社会評論社。2000年)
- The Japanese Victims of Stalinist Terror in the USSR, Hitotsubashi Journal of Social Studie,No.32, No.1, July 2000.(英文最新版)
- 「ヨーロッパの社会主義」(『労働運動研究』375号、2001年1月)
 「戦後日本とアメリカの影」1998歴研大会報告決定版(『20世紀のアメリカ体験』青木書店、2001)
「戦後日本とアメリカの影」1998歴研大会報告決定版(『20世紀のアメリカ体験』青木書店、2001)- 「20世紀日本における 「人民」概念の獲得と喪失」(立命館大学『政策科学』2001年3月)
- 「イ ンターネット時代の集権と分権」 (『月刊東京』第212号、2001年3月15日)
- 「新たに発見された 『沖縄奄美非合法共産党資料』について」(『大原社会問題研究所雑誌』2001年4月 ・5月)(4月上PDF版 ・5月下PDF版 )
- 情報の森 を抜けて、交響の丘へ!──インターネットとマルクス主義(『季刊 アソシエ』第6号>、2001年3月、矢沢修次郎編『情報社会化に関する国際比較研究』科研報告書2001)
- 「戦後日本と 『アメリカ』の影──『いのち』と『くらし』のナショナル・デモクラシー」(歴史 学研究会編
- 『二〇世紀のアメリカ体験』青木書店、2001年、所収)
- 「小泉首相のメールマガ ジン、人気取りに走れば、手痛いしっぺ返し」(『エコノミスト』2001年6月26日)
- 「査問の背景」 (川上徹『査問』ちくま文庫版「解説」、2001年7月)
- 「一橋大学にとっての教養教育」(『AGORA』2001.10.1)

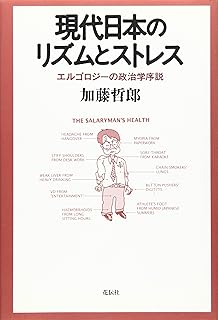
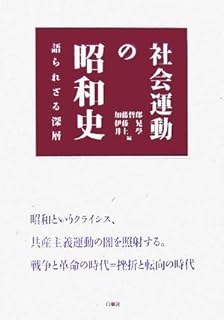
- <米国国立公文書館文書も用いて情報戦研究>
- 「9.11以後の世界と 草の根民主主義ネットワーク──アメリカ、日本、韓国関係の再編(『日韓教育フォ ーラム』第11号、2001年11月)」
- 「共同性・社会化の 模索──1950年代社会論」(2001年度歴史学研究会現代史部会大会報告批判、『歴史 学研究』第757号、2001年12月)
- 「消し去ることのできない 歴史の記憶──占領期領期沖縄・奄美非合法抵抗運動のシンポジウムから」 (『アソシエ21 ニューズレター』第32号、2001年12月号)
 「ネットワーク時代 に真のデモクラシーは完成するのか?」(『データ パル2002 最新情報用語資料事典』、小学館、2002年、ネ チズン・カレッジ版)
「ネットワーク時代 に真のデモクラシーは完成するのか?」(『データ パル2002 最新情報用語資料事典』、小学館、2002年、ネ チズン・カレッジ版)- 「人民」 (『講座 公共哲学 5 国家と人間と公共性』東京大学出版 会、2002年)
- 「新発見の河上肇 書簡をめぐって──国崎定洞と河上肇」(公開シンポジウム「コミンテルンと河上 肇」報告、『東京河上会会報』74号、2002年1月)
- 「幻の日本語新聞『ベル リン週報』を求めて ――サイバー・メヂィアによるクラシック・メディア探索記」(20世紀メディア研究会発行、紀伊国屋発行『INTELLIGENCE(インテリジェンス)』創刊号、2002年3月)
- 「社会政 策学会での日本の社会労働運動論議──栗木安延さんを追悼して」(『アソシエ 21 ニューズレター』第38号、2002年6月号)
- 「現代世界 の社会主義と民主主義」(『社会体制と法』第3号、2002年6月)
- 「ウ ェブ上に集った市民が現実政治を変えている」(『エコノミスト』2002年7月2 日号)
- 「日本の社 会主義運動の現在」(『葦牙』第28号、2002年7月)
- 「島崎蓊助 のセピア色と『絵日記の伝説』(桐生大川美術館『ガス燈』第53号、2002年7月 10日号)
- Japanese Regulation and Governance in Restructuring: Ten Years after the ‘Post-fordist Japan’ Debate, Hitotsubashi Journal of Social Studies, No.34, No.1, July 2002.(英文改訂版)
- 「島崎蓊助と竹久夢二──ナチ ス体験の交錯』(桐生『大川美術館・友の会ニュース』第49号、2002年8月)
- 現代日本社 会における「平和」──情報戦時代の国境を越えた「非戦」」(『歴史学研究』 第769号、2002年11月
- 「芹沢光治良と友人た ち──親友菊池勇夫と『洋行』の周辺」(『国文学 解釈と鑑賞、特集 芹沢光治良』第68巻3号、 2003年3月)
- 「国家論」 (『AERAMOOK 新版 政治学がわかる』朝日新聞社、2003年、所収)
- 「幻の日本語新聞『伯林 週報』『中管時報』発見記(20世紀メディア研究会発行、紀伊国屋発行『INTELLIGENCE(インテリジェンス)』第2号、2003年3月)
- 「9.11以 後の情報戦とインターネット・デモクラシー」(公共哲学ネットワーク編『地球的平和の公共哲学──「反テロ」世界戦争に抗して』(東京大学出版会、2003年5月)
- 「反ダボス 会議のグローバリズム」(『エコノミスト』「学者が斬る114」2003年5月13日 号)
- 「情報戦時 代の世界平和運動」(『世界』2003年6月臨時増刊号)
- 「マルチチュードは国境を越えるか?──政治学から『帝国』を読む」(『情況』2003年 6月号)
- 「情報戦時代の『帝国』ア メリカ包囲網──インドで世界社会フォーラムを考える」(『葦牙』29号、 2003年7月)
- 「グロ ーバリゼーションは福祉国家の終焉か――ネグリ=ハート『帝国』への批判的評注」 (『一橋論叢』130巻4号、2003年10月)
- 「グローバ ル情報戦時代の戦争と平和――ネグリ=ハート『帝国』に裏返しの世界政府を見る」 (日本平和学会『世界政府の展望(平和研究第28号)』、2003年11月)
- 「21世 紀から『戦後史』研究を考える」(『静岡県近代史研究』第29号、2003年 10月)
- 20世紀日 本の社会主義と第一次共産党(月刊『社会主義』2004年2月号)
- 「もう一つの世界は可能だ」(『月刊東京』2004年2月)
- 戦後天皇制 をめぐる毛沢東、野坂参三、蒋介石(インターネット版)(「『野坂参三・毛沢 東・蒋介石』往復書簡」『文藝春秋』 2004年6月号のネット版)
- 反骨の在 米ジャーナリスト岡繁樹の1936年来日と偽装転向(20世紀メディア研究所『イン テリジェンス(INTELLIGENCE)』第4号、紀伊国屋書店、2004年5月)
- 大義の摩滅 した戦争、平和の道徳的攻勢――『アブグレイブの拷問』をめぐる情報戦 (『世界』2004年7月号)
- グローバルな世 界と<私たち>の従軍(『従軍のポリティクス』青弓社、2004年7月、所 収、インターネット版)
- 「新史料発見 194 2年6月米国『日本プラン』と象徴天皇制」(『世界』2004年12月号)
- 「イラク 戦争から見たゾルゲ事件 」(ゾルゲ・尾崎秀実没後60周年記念講演、日露歴史研究センター講演録『現 代の情報戦とゾルゲ事件』、2005年4月)
- 「21世紀に日韓現代 史を考える若干の問題――1942年の米国OSSから2004年の東アジアOSS へ」(『第7回日韓歴史共同研究シンポジウム報告』2005年4月)
- ヴィクトー リア手記の教えるもの(『山本正美治安維持法裁判陳述集』解説、新泉社2005年 7月刊)
- 社会民主党宣言から日本国憲法へーー日本共産党22年テーゼ、コミンテルン32年テー ゼ、米国OSS42年テーゼ(『葦牙』第31号、2005年7月)
- 「グローバリゼーショ ンと情報」(聖学院大学総合研究所紀要第33号、2005)
- 「護憲・論憲・改憲の幅 と収縮可能性」(日本民主法律家協会『法と民主主義』2006年1月号)
- 「体制変革と情報戦――社会民主党宣言から象徴天皇制まで」(岩波講座『「帝国」 日本の学知』第4巻『メディアのなかの「帝国」』岩波書店、2006年)
 「戦争と革命ーーロシア、中国、ベトナムの革命と日本」(『岩波講座 アジア・ 太平洋戦争』第8巻『20世紀の中のアジア・太平洋戦争』i岩波書店、200 6年)
「戦争と革命ーーロシア、中国、ベトナムの革命と日本」(『岩波講座 アジア・ 太平洋戦争』第8巻『20世紀の中のアジア・太平洋戦争』i岩波書店、200 6年) 『党創立記念日』という神話」(加 藤哲郎・伊藤晃・井上學編著『社会運動の昭和史――語られざる深層』白順社 、2006、所収)
『党創立記念日』という神話」(加 藤哲郎・伊藤晃・井上學編著『社会運動の昭和史――語られざる深層』白順社 、2006、所収)- 「国家権力と 情報戦――『党創立記念日』の神話学」(『情況』2006年6月号)
 「モンゴルで 「小国」の自立の知恵を考える」(『情況』2006年8月号)
「モンゴルで 「小国」の自立の知恵を考える」(『情況』2006年8月号)- 「国際情報戦の中のゾルゲ =尾崎秀実グループ」(『 労働運動研究』復刊第14号、2006年8月)
- Personal Contacts in German–Japanese Cultural Relations during the 1920s and Early 1930s , in, “Japanese-German Relations, 1895-1945 War, Diplomacy and Public Opinion” (Edited by: Christian W. Spang, Rolf-Harald Wippich , Routledge 2006(Internet version)
- 「グローバリゼーションと 国民国家」(『社会理論研究』第7号、2006年11月)
- 「<天皇制民主主義>論」(松村高夫・高草木光 一編『連続講義 東アジア 日本が問われていること』岩波書店、2007年3 月)
 「インターネットーー情報という疑似環境」(渡辺雅男・渡辺治編『「現代」という環境』旬報社、2007年3月)
「インターネットーー情報という疑似環境」(渡辺雅男・渡辺治編『「現代」という環境』旬報社、2007年3月)- 「ポスト国民国家 時代における労働市場の変容と男性性」(『情 況』2007年5/6月)
- 「グローバルな地球社会のナショナルな国家」(尾崎行雄記念財団『世界と議会』第518号、2007年11月)
- 「情報戦のなかの『亡命』知識人ーー国崎定洞から崎村茂樹まで」(20 世紀メディア研究所『A>インテリジェンス』誌第9号、2007年11月)
 「大学ランキングと一橋大学の取組み」(一橋大学)(IDE大学協会『IDE 現代の高等教育』第495号、2007年11月)
「大学ランキングと一橋大学の取組み」(一橋大学)(IDE大学協会『IDE 現代の高等教育』第495号、2007年11月) 「ヴァイマール・ドイツの日本人知識人」(工藤章・田嶋信雄編『日独関係史』第3巻「体制変動の社会的衝撃」、東京大学出版会、2008年3月)
「ヴァイマール・ドイツの日本人知識人」(工藤章・田嶋信雄編『日独関係史』第3巻「体制変動の社会的衝撃」、東京大学出版会、2008年3月) 「グローバル・デモクラシーの可能性ーー世界社会フォーラムと『差異の解放』『対等の連鎖』」(加藤哲郎・国廣敏文編『グローバル化時代の政治学』法律文化社、2008年3月、所収)
「グローバル・デモクラシーの可能性ーー世界社会フォーラムと『差異の解放』『対等の連鎖』」(加藤哲郎・国廣敏文編『グローバル化時代の政治学』法律文化社、2008年3月、所収)- 「ゾルゲ事件の残された謎」(日露歴史研究センター『ゾルゲ事件外国語文献翻訳集』第19号、2008年6月)
- 「『社会主義』中国という隣人」(『葦牙』第34号、2008年7月)
- ‘Politicas de la pandemia en Mexico y Japan‘(“Bulletnin CEAA”Mayo,2009, El Colegio de Mexico)
- 「疑心暗鬼の国が生んだ人間のドラマ」(静岡県舞台芸術センター『劇場文化』9号 、2009年6月)
- 「ハーン・マニアの情報将校ボナー・フェラーズ」(平川祐弘・牧野陽子編『ハーンの人と周辺』新曜社、2009年8月)
- 「戦後日本の政治意識と価値意識」、渡辺雅男編『中国の格差、日本の格差』(彩流社、2009年11月)
- 「日本近代化過程におけるマルクス主義と社会主義運動の遺産」、『Forum Opinion』No.7, 2009年12月



- <早稲田大学客員教授、インテリジェンス研究>
- 「ゾルゲ事件の新資料ーー米国陸軍情報部(MIS)『木元伝一ファイル』から」(日露歴史研究センター『ゾルゲ事件外国語文献翻訳集』第25号、2010年3月)
- 「『世界のトヨタ』揺籃期の企業文化」(『占領期雑誌資料体系 文学編』第3巻「月報」,2010年3月)
- 「戦後米国の情報戦と60年安保ーーウィロビーから岸信介まで」(『年報 日本現代史』第15号、現代史料出版、2010年6月)
- 「ゾルゲ事件の3つの物語ーー日本、米国、旧ソ連」(日露歴史研究センター『ゾルゲ事件関係外国語文献翻訳集』第26号、2010年6月)
- 「アメリカニズムと情報戦」(『葦牙』第36号、2010年7月)
 菅孝行・加藤哲郎・太田昌国・由井格「鼎談 佐野碩ーー一左翼演劇人の軌跡と遺訓(上)(下)」(『情況』2010年8・9月、10月)
菅孝行・加藤哲郎・太田昌国・由井格「鼎談 佐野碩ーー一左翼演劇人の軌跡と遺訓(上)(下)」(『情況』2010年8・9月、10月)- 「新発掘資料から見たゾルゲ事件の実相」(日露歴史研究センター『ゾルゲ事件関係外国語文献翻訳集』第28号、20
- 「連合国の戦後アジア構想」(『岩波講座 東アジア近現代通史 第6巻 アジア太平洋戦争と「大東亜共栄圏」1935−45年』岩波書店、2011年1月)
- 「日本共産党とコミンフォルム批判」(『岩波講座 東アジア近現代 通史 第7巻 アジア諸戦争の時代」1945-60年』岩波書店、2011 年2月)
- 「社会民主主義の国際連帯と生命力ーー1944年ストックホルムの 記録から」(『未来』第541号、2011年10月)
- 「宮城與徳訪日の周辺ーー米国共産党日本人部の2つの顔」(日露歴 史研究センター編・第6回ゾルゲ事件国際シンポジウム報告集『ゾルゲ事件と 宮城與徳を巡る人々』2011年10月)
- 「亡命者佐野碩ーー震災後の東京からベルリン、モスクワへ」(The Art Times, No.3, October 2011)
- 「福本イズムを大震災後に読み直す」(『「福本和夫著作集』完結記念の集い・報告集』こぶし書房、2011年10月)
- 「日本マルクス主義はなぜ『原子力』にあこがれたのか」ウェブ版データベース(同時代史学会2011年年次大会報告)
- 「世界から見た日本のいま」(『季刊 ピープルズ・プラン』56号、2011年12月)
- 「占領下日本の情報宇宙と『原爆』『原子力』ーープランゲ文庫のもうひとつの読み方」(『インテリジェンス』誌第12号、文生書院。2012年3月)
- 「占領下日本の『原子力』イメージーー原爆と原発にあこがれた両義的心性」(歴史学研究会編『震災・核災害の時代と歴史学』、青木書店、2012年6月)
- 「『原子力村』生成の歴史的根拠を曝く」(『場』43号、2012年9月)
- 「原爆と原発から見直す現代史」(『エコノミスト』10月8日臨時増刊号「戦後世界史」)
- 「社会民主主義の国際連帯と生命力ーー1944年ストックホルムの 記録から」(田中浩編『リベラル・デモクラシーとソーシャル・デモクラシー 』未来社、2013年1月、所収)
- 「金澤幸雄さんと金澤資料について」(「森宣雄・鳥山淳編『「島ぐるみ闘争」はどう準備されたのかーー沖縄が目指す<あま世>への道』(不二出版、2013年9月)
 チャルマーズ・ジョンソン・新訳『ゾルゲ事件とは何か』(岩波現代文庫、2013年9月)加藤「解説」
チャルマーズ・ジョンソン・新訳『ゾルゲ事件とは何か』(岩波現代文庫、2013年9月)加藤「解説」 歴史学研究会2013大会震災特設部会「大会報告批判」(『歴史学研究』2013年12月号)「国際情報戦としてのゾルゲ事件」(『ゾルゲ事件外国語文献翻訳集』38号、2013年12月刊)
歴史学研究会2013大会震災特設部会「大会報告批判」(『歴史学研究』2013年12月号)「国際情報戦としてのゾルゲ事件」(『ゾルゲ事件外国語文献翻訳集』38号、2013年12月刊)- 「社会民主主義の国際連帯と生命力 崎村茂樹研究②」田中浩編『リベラル・デモクラシーとソーシャル・デモクラシー』未来社。2013年
- インタビュー1970年代「エピローグとなった『序説』への研究序説ーー『スターリン問題研究序説』と70年代後期の思潮」(中部大学年報『アリーナ』第16号、2013)
- 「国崎定洞ーー亡命知識人の悲劇」(安田常雄ほか編『講座 東アジアの知識人 第4巻 戦争と向き合って』有志舎、2014年3月、所収)
- 「機密解除文書が明かす戦後日本の真の姿:GHQ文書」(『週刊 新発見 日本の歴史』44号、2014年5月18日)
- (井関正久と共著)「戦後日本の知識人とドイツ」(工藤章・田嶋信雄編『戦後日独関係史』東京大学出版会、2014年6月
- 「『国際歴史探偵』の20年ーー世界の歴史資料館から」(法政大学『大原社会問題研究所雑誌』670号、2014年8月号
- 「戦後ゾルゲ団、第二のゾルゲ事件 の謀略?」(第8回ゾルゲ事件国際シンポジウム報告、「ゾルゲ・尾崎処刑70周年ー新たな真実」2014年11月8日、東京・明治大学)日露歴史研究センター『ゾルゲ事件外国語文献翻訳集』第42号、2015年2月
- 「島崎藤村・蓊助資料の寄贈に寄せて」『日本近代文学館報』第265号(2015年5月)
- 「現代史史料としての『労働運動研究』誌 」(労働運動研究所の『労働運動研究』誌総目次、推薦文、2015年6月)
- 「米国の占領政策ーー検閲と宣伝」(波多野・東郷編『歴史問題ハンドブック』岩波現代全書、2015年6月)
- 「占領期における原爆・原子力言説と検閲」(木村朗・高橋博子編『核時代の神話と虚像』明石書店、2015年7月)
 「コミンテルンと佐野碩」(菅孝行編『佐野碩 人と仕事(1905−1966)』藤原書店、2015年12月)
「コミンテルンと佐野碩」(菅孝行編『佐野碩 人と仕事(1905−1966)』藤原書店、2015年12月) 「第9回ゾルゲ事件シドニー国際シンポジウム参加記」英文報告「Richard Sorge Case and Unit 731 of the Imperial Japanese Army」(日露歴史研究センター『ゾルゲ事件外国語文献翻訳集』第45号、2016年2月)
「第9回ゾルゲ事件シドニー国際シンポジウム参加記」英文報告「Richard Sorge Case and Unit 731 of the Imperial Japanese Army」(日露歴史研究センター『ゾルゲ事件外国語文献翻訳集』第45号、2016年2月)- 講演記録「戦争の記憶ーーゾルゲ事件からシベリア抑留へ」(日露歴史研究センター『ゾルゲ事件外国語文献翻訳集』第46号、2016年5月)
- 「五族協和の内実を問う」『こころ』2016年
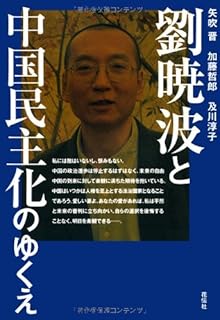
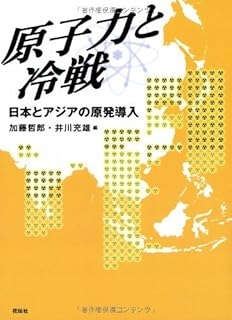

 <ゾルゲ事件・731部隊研究・パンデミック>
<ゾルゲ事件・731部隊研究・パンデミック>- 講演記録「ゾルゲ事件と伊藤律ーー歴史としての占領期共産党」(日露歴史研究センター『ゾルゲ事件外国語文献翻訳集』第47号、2016年8月
- 「人権優先の『世界共和国』へ」(広井良典・大井浩一編『2100年へのパラダイム・シフト』作品者、2017年3月)
- 「現代社会科学の一部となったグラムシ」(『唯物論研究』139号、2017年5月)
- 「米国共産党日本人部研究序説」(藤井一行教授追悼寄稿、中部大学『アリーナ』第20号、2017年11月)
- 「731部隊の隠蔽・免責・復権」(週刊金曜日編『加害の歴史に向き合う』2017年12月)
- 「大学のグローバル化と日本の社会科学」(信州大学『イノベーション・マネージメント研究』13号、2018年3月)
- 「戦後保守政権の改憲動向」(『週刊金曜日』2018年7月13日号)
 「バクー生まれのリヒアルト・ゾルゲーー独立と支配に必要な諜報機関の英雄」(廣瀬陽子編『アゼルバイジャンを知るための67章』2018年8月)
「バクー生まれのリヒアルト・ゾルゲーー独立と支配に必要な諜報機関の英雄」(廣瀬陽子編『アゼルバイジャンを知るための67章』2018年8月) 「731部隊員・長友浪男軍医少佐の戦中・戦後」(戦医研『15年戦争と日本の医学医療研究会(戦医研)会誌』19巻2号、2019年5月)
「731部隊員・長友浪男軍医少佐の戦中・戦後」(戦医研『15年戦争と日本の医学医療研究会(戦医研)会誌』19巻2号、2019年5月)- 「20世紀社会主義・革命運動史を21世紀にどう描くかーー河西英通著『「社共合同」の時代』に寄せて」(法政大学『大原社会問題研究所雑誌』737号、2020年3月)
- 「ゾルゲ事件ヴケリッチ家のオーストラリア」(20世紀メディア研究所『20世紀メディアよもやま話』文生書院、2020年4月)
- 「「日本のコロナ対応にみる731部隊・100部隊の影」(NPO法人731資料センター『会報』第37号、2021年10月)
- 「コミンテルン創立100年、研究回顧50年」(『初期社会主義研究』第29号、2021年3月)
- 「マルクス主義国家論の回顧・再論」(大阪唯物論研究会『唯物論研究』157号、2021年11月)
- 「戦前の防疫政策・優生思想と現代」(戦医研『戦争と医学』誌22巻,2021年12月)
- 「 コミンテルンの伝統と遺産」(東京唯物論研究会の『唯物論』誌96号、2022年12月)
- 「ゾルゲ事件についての最新の研究状況 2023」(映像編)(論文編)
- 「日本政治学史と田口富久治先生」(『追想 田口富久治』2023.11,寄稿文)
 「外交官岡本行夫の継承した父の731部隊体験」『山本武利著作集』第7巻「月報」(2025年7月、文生書院)
「外交官岡本行夫の継承した父の731部隊体験」『山本武利著作集』第7巻「月報」(2025年7月、文生書院)
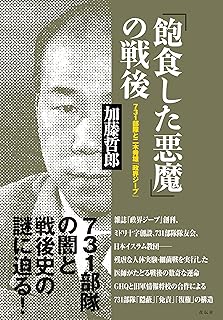
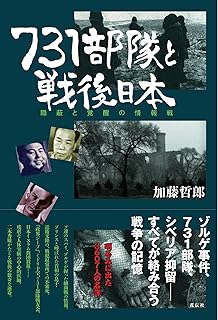

翻訳書
 フィッシャー =ポニア編集、ネグリ=ハート 序文『もうひとつの世界は可能だ! (Another World Is Possible )』(日本経済評論社、2003年)
フィッシャー =ポニア編集、ネグリ=ハート 序文『もうひとつの世界は可能だ! (Another World Is Possible )』(日本経済評論社、2003年)- B・ジェソップ『資本主義国家』(田 口富久治らと共訳、御茶の水書房、1984年)B・ジェソップ『プーランザスを読 む』(田口富久治らと共訳、合同出版、1987年)
- M・カーノイ『国家と政治理論』(黒沢惟昭らと共訳、御茶の水書房、1992 年)
- オーウェン・マシューズ著、鈴木規夫・加藤哲郎訳『ゾルゲ伝 スターリンのマスター・エージェント』(みすず書房、2023年)
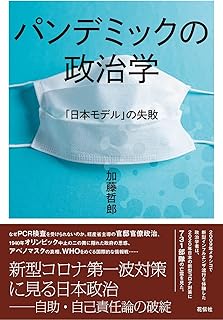


国内学会報告
- 「ネオ・コーポラティズム討論について」(日本政治学会19 82年度研究大会)
- 「『戦後』史への複眼的視角」(歴史学研究会1986年度研究大会)
- 「世界システムのなかの象徴天皇制」(唯物論研究協会1989年度研究大会)
- 「多国籍企業と国民国家」(日本政治学会1990年度研究大会)
- 「現代マルクス主義とリベラリズム」(日本政治学会1992年度研究大会)
- 「現代政治空間における 国家と民主主義」(経済地理学会1993年度大会)
- 「マルクス主義と市民 社会論」(日本政治思想学会1996年度大会)
- 「戦後日本と『アメリ カ』の影」(歴史学研究会1998年度研究大会)
- 「日本の社会主義運動の現在」(社会政策学会2002年度大会)
- 「グローバリゼーションと 国民国家」(社会理論学会、第13回大会基調報告、2005年、『社会理論研究』第7号、2006年11月)
- 「日本マルクス主義はなぜ『原子力』にあこがれたのか」ウェブ版データベース(同時代史学会2011年年次大会報告、2011年12月)
 「731部隊・長友浪男軍医少佐の戦前と戦後:厚生省優生保護法強制不妊手術担当から北海道副知事へ」(15年戦争と日本の医療・医学研究会2018年例会、2018年12月、you tube)」
「731部隊・長友浪男軍医少佐の戦前と戦後:厚生省優生保護法強制不妊手術担当から北海道副知事へ」(15年戦争と日本の医療・医学研究会2018年例会、2018年12月、you tube)」- 「「日本のコロナ対応にみる731部隊・100部隊の影」(NPO法人731資料センター第10回総会記念講演、『会報』第37号、2021年10月)

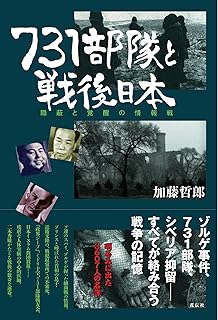

国際学会報告
- ‘Marxist Debates on the State in Post-war Japan’(with Fukuji Taguchi,世界政治学会第13回研究大会、1985年、パリ)
- ‘The Age of “Japamerica”‘(一橋大学社会学部第1回国際シンポジウム、1988年、東京)
- ‘Is Japanese Capitalism Post-Fordist?’(with Rob Steven, ニュージーランド・アジア研究学会第8回研究大会、1990年、クライストチ ャーチ)
- ‘Japanese Perception of the 1989 Eastern European Revolution’(オーストラリア日本研究学会第7回研究大会、1991年、キャン ベラ、及びヨーロッパ日本研究学会第6回研究大会、1991年、ベルリン)
- ‘Organisationstheorie Rosa Ruxumburgs’(ローザ・ルクセンブルク東京国際シンポジウム、1991年、東 京)
- 「過労死とサービス残 業の政治経済学」(日韓連帯シンポジウム、1993年、東京、及び復旦大学日 本研究所国際シンポジウム、1993年、上海)
- 「ポスト・フォード主義日本モデルからエコロジーとエルゴロジーへ」(日韓連 帯シンポジウム、1994年、ソウル)
- ‘The Political Economy of Japanese KAROSHI’(世界政治学会第16回研究大会、1994年、ベルリン)グラムシ没後60周年記 念シンポジウム参加記(1997年11月、東京)
- “The Theory of Capital Accumulation by Rosa Luxumburg and The Contemporary Capitalist Globalization: Comment on Dr. Dae-Hwan Kim’s Paper”(ローザ・ルクセンブルグ・シカゴ国際シンポジウム、1998年、シカ ゴ)
- “Japanische Kuenstler und Intellectuells in Berlin am Ende der Weimarer Republik”(ベルリン森鴎外記念館記念講演、1998年12月3日、ベルリン)
- Japan at the end of the 20th Century (fin de siecle),1as.Jornadas Culturales de Japon,(22-24 May,2000. El Colegio de Mexico、メキシコ大学院大学第1回日本文化週間招待記念講演、2000年5月 22-24日)
- 「戦後 日本の政治」(国際交流基金「中央アジア日本研究セミナー」基調講演、 2000年10月30日、11月1日・3日、ウズベキスタン、キルギス、カザフスタン)
- 「20世紀の夢と現 実:戦争・文明・福祉」(一橋大学社会学研究科主宰国際シンポジウム、2000年12月 2-3日、渡辺雅男と共編、彩流社、2002年)
- Japanese Regulation and Governance in Restructuring: Ten Years after the ‘Post-fordist Japan’ Debate, Paper presented to the International Conference “East Asian Modes of Development and Their Crises: Regulationist Approaches” (Tunghai University, Taichung, Taiwan, April 19-20, 2001)
- “Japanische Kuenstler und Intellectuells in Berlin am Ende der Weimarer Republik”(ベルリン森鴎外記念館記念講演、1998年12月3日、ベルリン
- 「日本の社会主義運動 の現在」(北京大学国際関係学院主催国際シンポジウム「冷戦後世界の 社会主義運動」2002年1月25-27日、中国・北京、『葦 牙』28号、2002年7月))
- Japanese Political Economy in Restructuring, Paper presented to the International Conference on “India and East Asia: Learning from Each Other”, March 27 -28, 2003, Department of East Asian Studies, UNIVERSITY OF DELHI, INDIA
- 「21世紀に日韓現代史を考える若干の問題――1942年の米国OSSから2004年の東アジアOSS へ」(第7回日韓歴史共同研究シンポジウム報告、2004年8月21日)
- Economic Restructuring and the Constitutional Politics in Japan, Paper presented to the 40 aniversario del Centro de Estudios de Asia y Africa de El Colegio de Mexico, Foro Cultural Mexico-Japon, Mexico City, Noviembre 10-17, 2004
- 「国際情報戦の中のゾルゲ =尾崎秀実グループ」(第4回ゾルゲ事件国際シンポジウム「ゾルゲ事件とノモンハ ン=ハルハ河戦争」報告。2006年5月、モンゴール)
- “Japanese Social Sciences in Transition: new institutional and methodological constellation after the collapse of the Cold War System”, Guest Lecture at the Annual Conference of the German Association of Social Science Research on Japan (VSJF) “Social Science Matters” from 10-12 November, 2006, Hamburg, Germany
- “Embracing Affluence: Values and Politics in Postwar Japan”, International Conference on India-Japan and Asia, Session II : Facing New Social Challenges, 26 September 2008, India International Centre, New Delhi, India
- “Japan in Global Crisis”,メキシコ大学院大学主催、在メキシコ日本大使館・国際交流基金後援国際シンポジウム「ラテンアメリカにおける日本研究」招待記念講演、 El Colegio de Mexico, Mexico City, Mexico Sept.2, 2009, El Colegio de Mexico, Mexico City, Mexico
- 「宮城與徳訪日の周辺ーー米国共産党日本人部の2つの顔」(日露歴史研究センター編・第6回ゾルゲ事件国際シンポジウム報告集『ゾルゲ事件と 宮城與徳を巡る人々』2011年10月
- 「東日本大震災報道にみる日本と中国のメディア」(中国国際友人研究会=早稲田大学20世紀メディア研究所共催「中日マスメディアシンポジウム」2011年12月26−29日、北京・中国)
- Images of Atomic Energy in the Occupation Period of Japan: The Ambivalent Mentality for Atomic Bomb and Atomic Power”, New York University Workshop, March 19-20,2012,New York, USA”
- Why Japanese People could not avoid the Nuclear Plant Disaster: the Dream of Atomic Power and the Safety Myth from Hiroshima 1945 to Fukushima 2011″, The XII International Congress of Latin American Association for Asian and African Studies (ALADAA) , The international Symposium <Fukushima disaster and future of nuclear energy: Learning from the experiencec, June 13-15, 2012, Puebla, Mexico
- 「国際情報戦としてのゾルゲ事件」(第7回ゾルゲ事件国際シンポジウム=日中国際紅色情報戦シンポジウム、2013年9月15日、上海師範大学、『ゾルゲ事件外国語文献翻訳集』38号、2013年12月刊「戦後ゾルゲ団、第二のゾルゲ事件 の謀略?」(第8回ゾルゲ事件国際シンポジウム「ゾルゲ・尾崎処刑70周年ー新たな真実」2014年11月8日、東京・明治大学、日露歴史研究センター『ゾルゲ事件外国語文献翻訳集』第42号、2015年2月)
- “Richard Sorge Case and Unit 731 of the Imperial Japanese Army”,9th International Symposium on Richard Sorge Dec.4 2015,University of Technology in Sydney (UTS), Sydney(第9回ゾルゲ事件国際シンポジウム参加記,2015年12月)
- The war of Information about biological warfare by unit 731 of the Kwantung Army, Cambridge workshop: Propaganda and Journalism during/on the second Sino-Japanese War 1937-1945,The Wienrebe Room, Westminster College, Cambridge university,UK, March 19-21, 2018